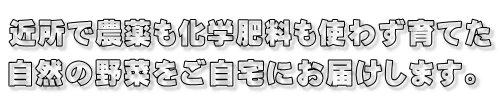有機農産物の流通
第1回のコラムは、有機農産物の流通についてお話したいと思います。
一般的な野菜の流通は全国の各都市にある卸売市場を通じて行われます。まず、生産者は地域にある農協に野菜を出荷しますが、そこで選別され、規格に合った野菜のみをひとまとめにして市場に送り出されます。S、M、L、LLといった表示ができるのは、農協で厳しい選別が行われるからです。ただし、この選別は、あくまでサイズという外観だけのもので、中身についての選別ではありません。
有機農産物は、自然に近い栽培をすればするほど形やサイズは不揃いに育ちます。何故かというと、一般的な栽培では化学肥料で均一に栄養を与えることができますが、自然の土では肥沃度が均一ではなく、どうしても成長にバラつきがでるからです。このため外観での規格化が難しく、一般市場では規格外として扱われることが多く、結果として安値で取り引きされてしまいます。努力を重ねて農薬や化学肥料を使わずに栽培した野菜が市場では評価されないため、ほとんどの有機栽培者は卸売市場に野菜を出荷することはありません。
では、どうやって有機農産物は流通されているのかというと、基本的には生産者個人に委ねられています。全国的に有機野菜のセット販売する会社もありますが、全体としては微々たるものです。その多くは近くの道の駅のような直販所に自ら出荷するか、直接消費者に宅配するなどの方法を使い野菜を売っています。姿かたちよりも中身を重視する消費者はそのようなルートからしか確かな有機農産物を購入することができません。
本来ならば、サイズの規格だけでなく中身重視で卸売市場が有機農産物を扱ってくれれば良いのですが、流通量が少ないという面もあり、なかなか実現しないのが現状です。現在、有機農産物の生産量は全体の0.4%にすぎないと言われています。安全で品質の良い野菜を求める消費者は決して少なくないと考えると、需要と供給のバランスを如何にとっていくかが課題となっています。限られた供給とそれを求める需要が上手にマッチングすることが、今後の有機農業の発展には欠かせません。